

交通遺児育英会の事業の目的は定款の第3条目的の項に定める通り、道路における交通事故が原因で亡くなられたか重度の障害を負われた方の子女のうち、経済的理由によって修学が困難な方々に対して奨学金の貸与等を行い社会有用の人材を育成することにあります。これまでこの前提をもとに修学支援の充実を図ってきました。それを進めるのに常に私たちの視野の中心にあるのは奨学生の方たちが社会に出られてからの奨学金返還の負荷を出来得る限り軽くすること、学費外であっても学生生活から社会に出るまでに常識的に必要とされる経費負担を軽減することです。
この発想を前提として、昭和53年から日野の豊田に東京寮“心塾”を開設し、平成17年からはその“心塾”を関西圏へ拡大しました。
平成末から、令和初期にかけては次のような給付型支援の拡大を図ってきました⇒給付型の奨学金の導入、自宅外通学者への家賃補助、上級学校進学受験費用補助、自動車運転免許取得費用補助、コロナ感染拡大に対応するための一時金給付等です。
令和6年度からは、浪人生の皆さんに対しての奨学金支援、全奨学生を対象とする英検受験費用補助をスタートしました。さらに令和7年度からはフランス語、ドイツ語、中国語など他の外国語も補助対象に加え、簿記やIT系、医療系などの各種資格試験についても受験回数、金額に上限を設けずに全額支給しています。
これら給付型の修学支援の多くと奨学制度の改善は“高校奨学生と保護者のつどい”(以下“つどい”と称す)や“語らいカフェ”等における保護者のご意見、提言をヒントにしてスタートしています。その意味でこれからも“つどい”や“語らいカフェ”のような保護者同士の交流、その場は取りも直さず私たち事務局との交流の場ともなっていますが、これを大事にし、そこから得たアイデアに絶えず我々独自の発想による改善、改革をプラスして事業を一歩ずつ前に進めていきます。
「心塾」では、専門家による「読書感想文講座」「文章講座」「スピーチ講座」を開講(関西寮は「読書感想文講座」のみ)、さらに年間を通して塾生同士や地域の人たちとの交流を図る様々な行事を実施しています。
| 役職 | 氏名 | 就任期間 |
| 会長 | 永野重雄 | S44 → S59 |
| 武田豊 | S59 → H6 | |
| 林健太郎 | H11 → H15 | |
| 清水司 | H18 → H29 | |
| 菅谷定彦 | R1 → R5 | |
| 石橋健一 | R5 → | |
| 理事長 | 石井栄三(官) | S44 → H6 |
| 宮崎清文(官) | H6 → H19 | |
| 中根晃 | H19 → H25 | |
| 菅谷定彦 | H25 → R1 | |
| 石橋健一 | R1 → R5 | |
| 土肥寿員 | R5 → | |
| 専務理事 | 玉井義臣 | S44 → H6 |
| 穴吹俊士 | H8 → H19 | |
| 石橋健一 | H19 → R1 | |
| 土肥寿員 | R1 → R5 | |
| 大屋克文 | R5 → |
| 1969年(昭和44年) | 5月 | 財団法人「交通遺児育英会」設立 初代会長に永野重雄、初代理事長に石井栄三が就任 |
| 9月 | 高校奨学金を月額5,000円としてスタート | |
| 1970年(昭和45年) | 7月 | 「高校奨学生のつどい」始まる |
| 1971年(昭和46年) | 3月 | 全国共済農業協同組合連合会が募集していた人形型募金箱の愛称が『さっちゃん』と決まる。佐藤栄作首相による命名。 |
| 1972年(昭和47年) | 3月 | 機関紙「君と581-2271」創刊号発行 |
| 1973年(昭和48年) | 4月 | 大学奨学金を月額20,000円としてスタート |
| 1975年(昭和50年) | 8月 | 「褒章条例に関する内規」による「公益団体」に認定される |
| 1977年(昭和52年) | 4月 | 大学院奨学金を月額50,000円としてスタート |
| 1978年(昭和53年) | 4月 | 学生寮竣工(東京都日野市)「心塾(こころじゅく)」と命名 第1回入塾式 41人入塾 高校・大学「入学一時金」制度スタート |
| 1979年(昭和54年) | 4月 | 「あしながおじさん奨学金制度」始まる 「あしながおじさん2,000人募集キャンペーン」スタート |
| 5月 | 「交通遺児育英会10年史」発刊 | |
| 1980年(昭和55年) | 2月 | 学生寮「心塾」で第1回卒塾式 8人卒塾 |
| 1981年(昭和56年) | 4月 | 専修学校・各種学校奨学金を月額30,000円としてスタート |
| 1982年(昭和57年) | 6月 | 「あしながおじさん」3,000人突破 |
| 1990年(平成2年) | 4月 | 「交通遺児育英会20年史」発刊 |
| 1994年(平成6年) | 3月 | 「心塾15年史」発刊 |
| 12月 | 「高校奨学生のつどい」中止を決定 | |
| 2000年(平成12年) | 3月 | 「高校奨学生のつどい」を新たに「高校奨学生と保護者のつどい」として各地区ごとに復活開催 |
| 2001年(平成13年) | 7月 | 「高校奨学生と保護者の相談会」始まる |
| 9月 | 機関紙の題号を「君とつばさ」に改題 | |
| 2002年(平成14年) | 1月 | ホームページ開設 |
| 4月 | 専修学校・各種学校「入学一時金」制度スタート | |
| 2004年(平成16年) | 4月 | 「あしながおじさん奨学金制度」満25周年 |
| 7月 | 「海外語学研修」スタート 高校奨学生29人が英国・ソールズベリーへ | |
| 2005年(平成17年) | 9月 | 学生寮心塾「関西寮」開設 |
| 2006年(平成18年) | 4月 | 学生寮心塾「関西寮」 第1回入塾式 7人入塾 |
| 10月 | 「進学準備金」制度スタート | |
| 2007年(平成19年) | 3月 | 「交通遺児育英会35年史」発刊 |
| 2008年(平成20年) | 5月 | 学生寮心塾「所沢寮」開設 |
| 2011年(平成23年) | 4月 | 「公益財団法人」に移行 |
| 2012年(平成24年) | 8月 | 地区ごとに開催してきた「高校奨学生と保護者のつどい」をこの年度から全国対象一括開催とした。(千葉市) |
| 2013年(平成25年) | 8月 | 「高校奨学生と保護者のつどい」開催(東京都) 以降、開催地を東京とし、個別相談会も併せて実施 |
| 2014年(平成26年) | 11月 | 交通遺児家庭の生活実態に関するアンケート調査を開始 |
| 2015年(平成27年) | 3月 | 平成26年度「交通遺児家庭の生活実態調査」報告書を発行 |
| 7月 | 「AC広告」第1弾スタート | |
| 10月 | 「家賃補助」制度スタート | |
| 2016年(平成28年) | 7月 | 「AC広告」第2弾スタート |
| 2017年(平成29年) | 3月 | 交通遺児とその母親の思いを綴った小冊子「父の思い出を乗り越えて」を発行 |
| 4月 | 「上級学校進学受験費用補助」制度スタート 「特別支援学校卒業生および生活保護受給者対象の返還免除」制度スタート | |
| 7月 | 「AC広告」第3弾スタート | |
| 2018年(平成30年) | 4月 | 「自動車運転免許取得費用補助」制度スタート |
| 7月 | 「AC広告」第4弾スタート | |
| 2019年(令和元年) | 5月 | 創立50周年 |
| 2020年(令和2年) | 4月 | 奨学金の一部給付(高校・高専を除く)を開始(2万円/月) 学生寮心塾「武蔵境寮」開設 |
| 5月 | 「交通遺児育英会50年史」発刊 | |
| 6月 | コロナ対応支援金一人一律20万円を全奨学生に対して給付 | |
| 7月 | コロナ禍により「海外語学研修」中止 | |
| 8月 | コロナ禍により「高校奨学生と保護者のつどい」中止 | |
| 9月 | 「心塾東京寮の建替えに関するプロジェクト」発足 | |
| 11月 | 交通遺児家庭の生活実態に関するアンケート調査を開始 | |
| 12月 | コロナ対応支援金(2回目)一人一律10万円を全奨学生に対して給付 | |
| 2021年(令和3年) | 3月 | 令和2年度「交通遺児家庭の生活実態調査」報告書を発行 |
| 6月 | コロナ対応支援金(3回目)一人一律10万円を全奨学生に対して給付 小冊子(第二集)「ハンドルの重みは命の重み」を発行 | |
| 7月 | コロナ禍により「海外語学研修」中止 | |
| 8月 | コロナ禍により「高校奨学生と保護者のつどい」中止 | |
| 2022年(令和4年) | 3月 | コロナ対応支援金(4回目)一人一律10万円を全奨学生に対して給付 心塾東京寮を建替えのため閉鎖 |
| 7月 | コロナ禍により「海外語学研修」中止 | |
| 8月 | コロナ禍により「高校奨学生と保護者のつどい」中止 | |
| 10月 | コロナ対応支援金(5回目)一人一律10万円を全奨学生に対して給付 | |
| 11月 | 「語らいカフェ」スタート | |
| 2023年(令和5年) | 4月 | 高校および専修学校高等課程等の奨学生に奨学金の一部給付を開始(1万円/月) |
| 7月 | 「海外語学研修」再開 | |
| 8月 | 「高校奨学生と保護者のつどい」再開 | |
| 9月 | 「語らいカフェ」再開 | |
| 11月 | 「心塾®︎」新東京寮が竣工 | |
| 2024年(令和6年) | 2月 | 「心塾®︎」東京寮、全面リニューアル竣工式開催(3月より入寮) |
| 3月 | 奨学生の生活実態に関するアンケート(ヤングケアラー調査)を実施 | |
| 4月 | 「進学支援金」制度(浪人生への支援)、「英語検定試験費用補助」制度スタート |
| 名称 | 公益財団法人 交通遺児育英会 |
| 所在地 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-1 平河町ビル3階 |
| 電話 | 03-3556-0771(代表) |
| 設立 | 昭和44年(1969年)5月2日 |
| 役員 | |
| 会長 | 石橋 健一 |
| 理事長 | 小栗 洋 |
| 専務理事 | 大屋 克文 |
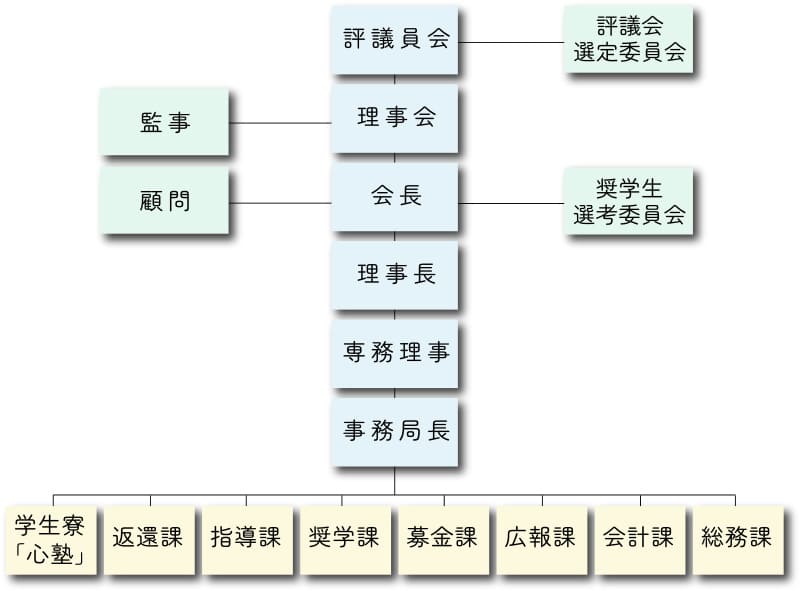
「交通遺児育英会」や「あしながおじさん」を名乗るメールやラインその他不審な勧誘にご注意ください。
当会では、個人に対して、メールやラインおよびフェイスブック等での勧誘は一切行っておりません。